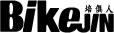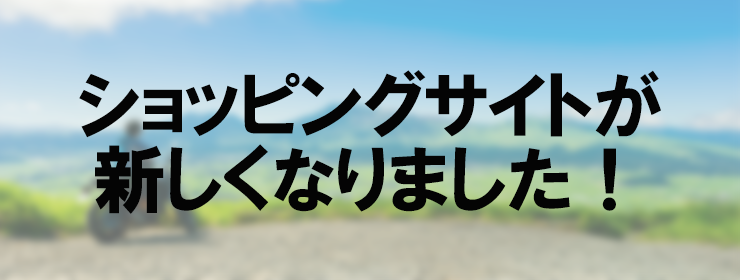なるほど!世界のバイク人「世界で異なるバイクの免許区分」
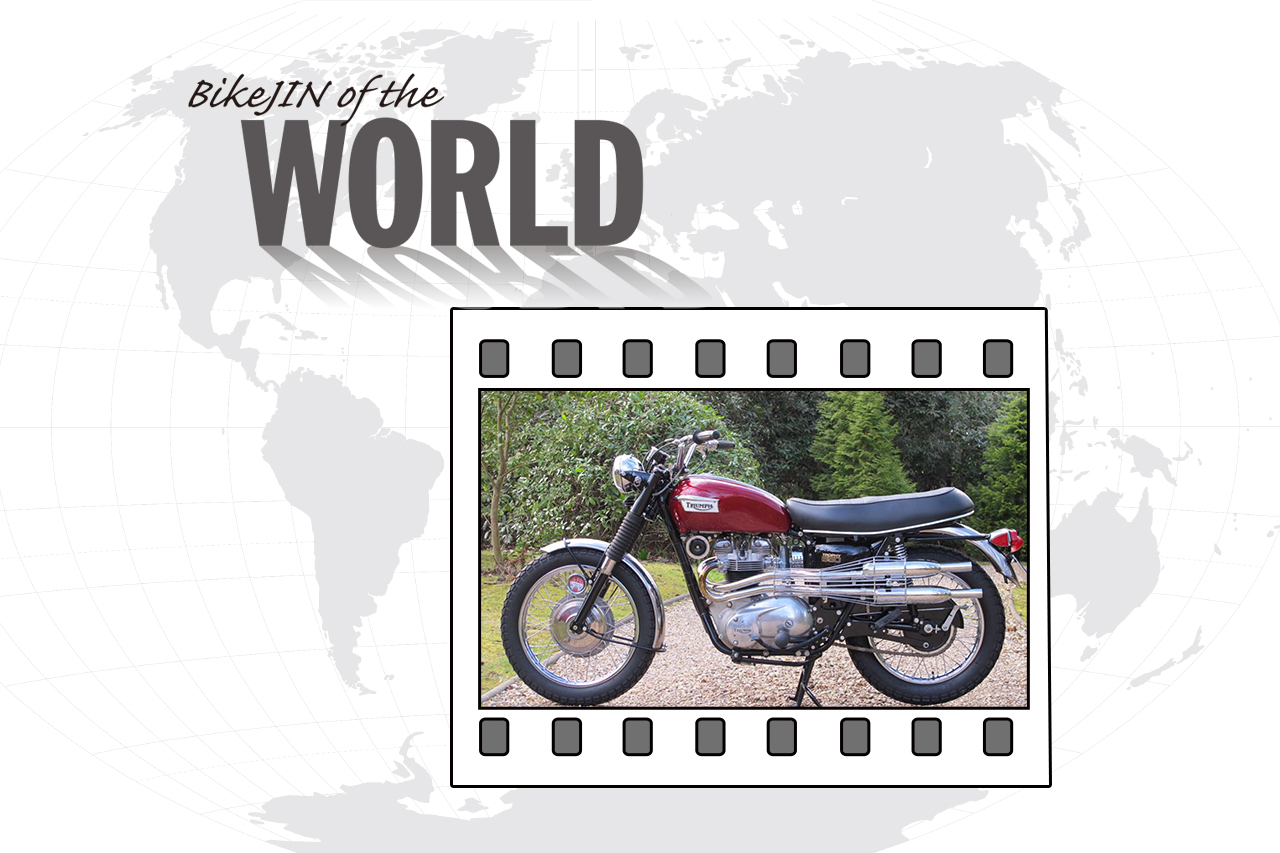
欧州の主流は最高出力に夜区分だ。70kwまでのモデルは35kwに調整すればA2ライセンスで運転可能となる。日本の排気量別とは似て非なる制度だ
※BikeJIN vol.264 2025年2月号参照
世界共通モデルとなった今免許制度も見直してよい
昔、まだ世界が今よりも単純だったころ、モーターサイクルを乗るのにドライビングライセンスはいらなかった。やがてライセンスが必要になったが、それは単に申請するだけでよく、初心者でも好きなだけ大きいバイクに乗ることができた。その後、ドライビングテストが行われるようになり、21世紀に入るとEEA/ヨーロッパ経済圏の各国でライセンスが統一され、当時はEU加盟国だったイギリスも同調した。
現在、EEAの30カ国とEU離脱後のイギリスで有効なエンジン付き2輪車のライセンスは、モペッドを除けばA1、A2、Aの3種類からなっている。この区分は、EEAの周辺国やアジアの国々にもコピーされていて、世界の他の地域もこれにならう動きがある。
バイク人の昔からの読者でこのコラムにときどき目を通している人なら、このライセンス制度は聞いたことがあるだろう。この制度の狙いのひとつは、相応のライディング技術が要求されるフルパワーのバイクに乗る前に、比較的低パワーのバイクを経験してパワーと技術のバランスを習得させ、ライダー自身の安全を高めることにある。
このシステムのポイントは、パワーを基準にして乗れるバイクを制限するという合理性だ。排気量の規定は最初のA1に125ccまでとあるだけで、A2にはない。それぞれのライセンスで乗れるバイクのパワーは、A1は11kW(14.75hp)以下でパワーウエイトレシオが0.1kW/kg以下。A2は35kW(47hp)以下で0.2kW/kg以下だ。Aライセンスには、A2経験が2年以上または24歳以上という以外、何も制限がない。
この中でもっとも汎用性があって融通が利くのはA2だ。なぜなら、35kW以上のバイクでも、70kWまでならリストリクターを装着して35kWに落とせば、A2ライセンスで乗れるからだ。だから、各メーカーがA2モデルとして販売しているバイク以外に、実際にリストリクターでA2リーガルにしているバイクも多い。例えば、カワサキ・ニンジャ650、ヤマハMT-07、ホンダCBR650R、スズキSV650などはそういうスポーツバイクの一例で、アドベンチャーでもカフェレーサーでも、70kWまでなら同じような処方箋でA2仕様にできる。
そのためのリストリクターは、ファクトリーキット以外にも運輸局に公認されたパーツが市販されているが、しかし、例えば70kWのリミットいっぱいのCBR650Rのパワーをリストリクターで50%も絞ったら、果たして走っておもしろいのだろうかという疑問はある。もちろん、2年間この状態で乗った後にAライセンスのテストに受かれば、リストリクターを外してフルパワーに戻せるので、改めてバイクを買わなくてもよいというメリットはあるが。
つまり、A2ライセンスで乗れるバイクは実際にはたくさんある。だから、あえて難しいAライセンスのテストを受けなくてもこれでいいや、と思うライダーも出てくるだろう。実際、バイクの選択肢という点では、ロードスターからスポーツバイク、アドベンチャー、レトロ、オフロードまですべてそろっているから、そういうケースは増えているらしい。しかも、価格はフルライセンスのバイクよりも手ごろで、保険も安い。だから、バイクの世界の長年の懸念であるバイクライダー人口の減少の緩和にも役立つのではないかと考える向きもある。
さて、日本にも同様の段階的な免許制度はある。むしろ日本の方が歴史は古い。ただし、その始まりにA2のような技術的裏付けはない。日本でバイクの中型免許が始まったのは今から半世紀前の1975年。それまでは125cc以下の小型自動二輪の上は自動二輪だけだったのだが、当時の社会問題だった暴走族を大型バイクから遠ざけるために、400ccという排気量の敷居が急ごしらえで設けられたのである。
なぜ中型免許が400ccになったのかは謎だ。当時、グランプリレーシングのクラス分けをもとにした伝統的な500ccの区切りが、市販車ではもはや重視されなくなっていたことは事実だが、しかし400ccという数字に、A2ライセンスのように安全を観点に据えたパワーと性能を根拠にした合理性はない。だから、57kW(76hp)も出る399cc4気筒に乗れる一方で、たった23.5kW(32hp)の500ccシングルには乗れないという、理不尽な事実がまかり通っているのだ。
私の疑問は、半世紀も続いている日本ならではのこの非合理性に、バイクライダー自身が疑いを持たないのかということだ。バイクに関する技術的知識が皆無で、自分で乗ったことすらなく、パワーとライダーの安全という観点で全体像を見られない官僚が思いついたとしか思えないこの400ccという区切りは、むろん世界的には何の意味もない。
にもかかわらず、最近は海外のメーカーからこの排気量に近いバイクがいくつも登場している。理由は簡単だ。これらはぜんぶA2バイクだからだ。排気量が400ccに近いのはたまたまで、日本の中型免許を参考にしたわけではない。これらのバイクのいくつかはパワーがまだA2の上限に達していないので、将来、もう少しパワーアップしたければ躊躇なく400ccを超えることもあるだろう。そのとき、日本のライダーはまた世界から取り残されることになる。
日本でしか通用しない免許制度を改めて、合理的な根拠がある国際基準に合わせるチャンスはいつでもある。中型免許がA2になれば、もっとたくさんのバイクが選択肢に上がることを、スペック表を見た読者は発見するだろう。