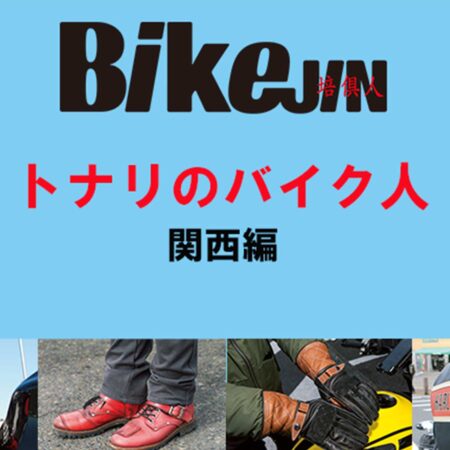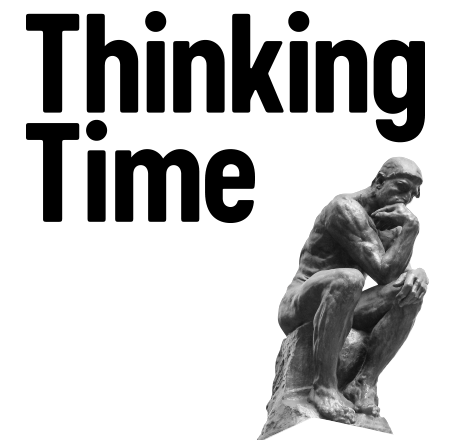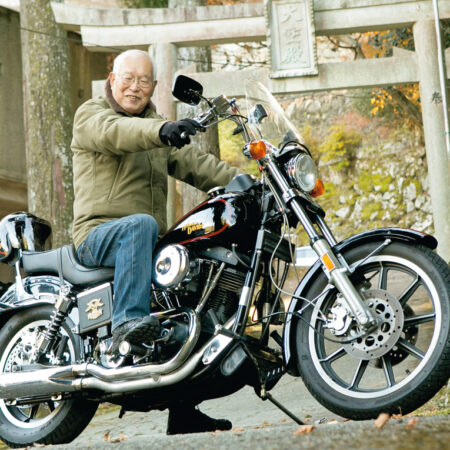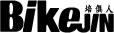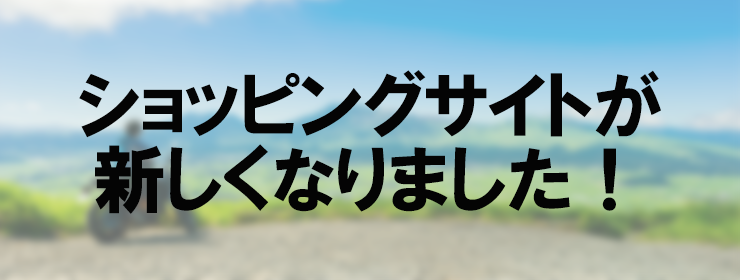【ツーリングガイド・富士五湖】人々はなぜ富士山に登るのか 富士山ヒストリーを学ぶ

富士五湖は元々富士八海だった!?
「なぜ人々は富士山に惹きつけられるのだろうか?」今まであまり興味がなかった僕に浮かんだ率直な疑問だ。そんなルーツが学べる場所があるというので早速向かってみた。その名も「ふじさんミュージアム」。名前は可愛らしいが富士山を取り巻く文化やそれにまつわる歴史などを知ることができるれっきとした博物館だ。
ふじさんミュージアム

富士信仰の歴史と文化を学ぶ博物館
富士山信仰の歴史や富士吉田の文化、人々の暮らしを実物の展示やタッチパネルなどで分かりやすく学べる。アカデミックなツーリングを楽しむならマストで立ち寄りたい場所。施設内には富士山要素満載のお土産コーナーもある
聞けば富士山は元々、神仏の住まう霊山として信仰のために登る山だったという。それが平安時代になると修験者たちが修行のために登るようになり、信仰登山として一般の人々が登るようになったのは室町時代以降のこと。江戸時代後期には庶民の間で富士山への参詣が大流行。このように古くから人々の心には富士山への畏敬の念が存在していたようだ。
なかでも僕が興味を引き付けられたのは江戸時代に流行したという富士講。現代とは比べ物にならないくらい費用と日数がかかることから、有志がお金を出し合い代表者が富士山を登る「講」という仕組みができあがり大衆に広まったそうだ。当時は日本橋から登山の出発地点である上吉田までの120㎞を3〜4日かけて歩いていたというから感慨深い。いまならバイクで2時間足らずで行けてしまう距離だ。文明の発達と技術の進歩を感じずにはいられない。そこで、当時の人々の足取りをたどるべく今回の旅の目的のひとつに富士の信仰登山ゆかりの地を巡ってみることにした。
富士講で富士山を訪れた人々は、神と信者の間に立ち祈りを捧げたり、自宅を宿泊所として提供する御お師しのもとに世話になったという。その御師の家々が並ぶ通りの入り口にあるのが「金鳥居い」だ。いわば富士山への入り口。いまでも民泊などを営んでいる元・御師の家もあるそうなので、宿泊して当時に思いを馳せてみるのも良いだろう。
金鳥居

富士山詣での入り口
鳥居の先の通り沿いには当時、富士山に参拝する人々を受け入れた御師(おし)が住まう家々が立ち並んでいた。最盛期である江戸時代後期には86軒もの御師の家が立ち並んでいたという
山梨県富士吉田市上吉田1-10付近
泉水

人々が富士登山前に身体を清めた
現在は水が枯れているが、当時は富士八湖にも数えられ、富士を詣でる人たちが身体を清める場所だった。道中はかなり路面が悪いので注意
山梨県富士吉田市上吉田
次に訪れたのは泉水。現在では水が枯れてしまっているが、当時は富士山に登る前に人々が水みず垢ご離り(身体を清めること)をするための湖だったという。周辺には駐車場もなく、泉水までの道はかなり路面状況が悪いため(ちなみに僕は途中でスタックしました)近くまで行ったらバイクを置いて徒歩で向かうのがオススメだ。この泉水に明見湖や四尾連湖を加えたものを、「富士八海」と呼び富士山への信仰登山のための禊の場として使われていた(時代によってほかの湖が入ってきたりもするそう)。
明見湖

富士山信仰における禊の場所
かつては泉水と同じく富士八湖に数えられ、富士山信仰の人々の身を清める場所、「垢離場(こりば)」であったといわれている。現在は蓮の葉で覆われており、通称「はす池」と呼ばれ地元の人々の憩いの場として利用されている
山梨県富士吉田市小明見5-4-15
TEL0555-22-1111
(富士吉田市役所環境政策課)
忍野八海

富士山の雪解け水が流れ入る神秘の池
出口池、お釜池、底抜池、銚子池、湧池、濁池、鏡池、菖蒲池の8つの池からなり、富士信仰の古跡霊場や禊の場としての歴史や背景から世界遺産富士山の構成資産の一部として認定された
山梨県南都留郡忍野村忍草
TEL0555-34-3111(忍野村役場)
ちなみに「富士五湖」と呼ばれるようになったのは割と最近で昭和に入ってからだという。そんな富士講の開祖である長谷川角行ゆかりの地である人穴富士講遺跡にも興味のある人は足を運んでみよう。
人穴富士講遺跡

富士講春麗の地
富士講の開祖長谷川角行が修行・入滅したとされる人穴風穴や富士講の信者たちによって建てられた230基もの碑塔群が残る。富士山が信仰の対象である価値を示す構成資産。碑からは各講の歴史や構成地域を知ることができる

静岡県富士宮市人穴206
TEL 平日0544-22-1111(富士宮市役所)
休日0544-52-1620
(人穴冨士講遺跡案内所)
営業時間:24時間
定休日:なし
北口本宮冨士浅間神社

富士吉田随一の浅間神社
県内に数ある浅間神社の中でも歴史は古く、なんと1900年以上。参道や境内には荘厳な雰囲気が漂っている。富士山の世界遺産の構成資産の1つでもあり、富士講の人々が富士山に登る前にこちらの神社にお参りしてから境内の登山門をくぐり富士山頂を目指したそうだ

山梨県富士吉田市上吉田5558
TEL0555-22-0221
営業時間:9:00〜16:30(祈祷受付)
定休日:なし